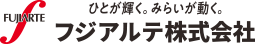派遣コラム
製造派遣スタッフを迎える前に確認したい、安全準備の落とし穴と対策
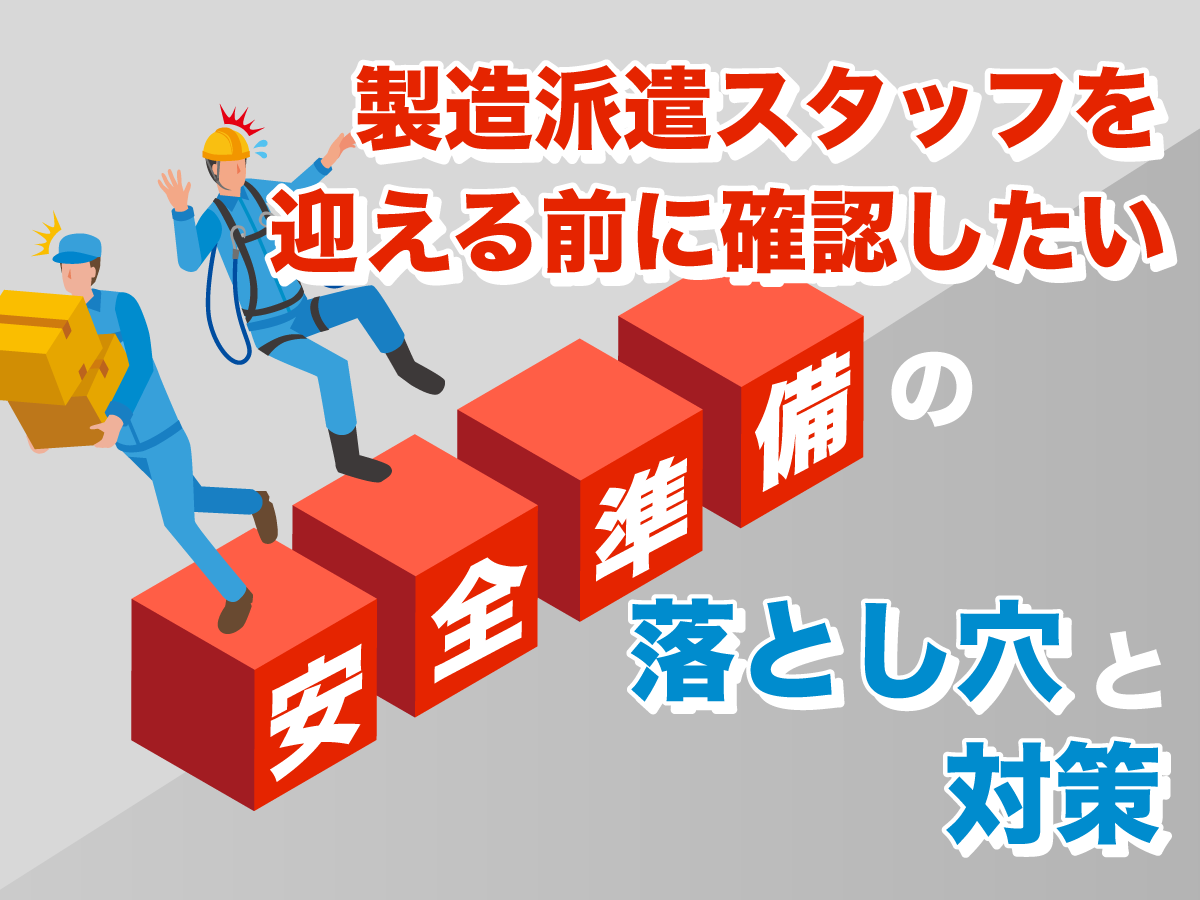
派遣スタッフの初日対応、安全面の準備はどこまで行うべきか――。
工程がひっ迫する中で、判断に迷う場面もあるかもしれません。
本記事では、見落とされがちな安全準備のポイントを、現場の事例をもとにご紹介します。
フジアルテでも、安全を最優先に取り組んでいます。
Q. このコラムでは何が書かれているの?
A. 製造現場で派遣スタッフを受け入れる際に、事故やトラブルを未然に防ぐために必要な安全教育・保護具・作業手順書の整備といった「受け入れ前の準備」のポイントについて、事例を交えながら解説しています。
Q. このコラムで最も大事なポイントは?
A. どれほど工程がひっ迫していても、 “安全だけは後回しにしない” という視点を持つことが、従業員の命と職場の信頼を守る鍵になります。フジアルテでは、派遣先企業様の安全衛生活動と歩調を合わせながら、就業前のすり合わせや情報共有を通じて、 “安全が前提となる現場づくり” を共に支えています。
Table of Contents
【例】金属加工メーカーA社の受け入れ対応
「簡単な作業だから」で済ませた初日対応の盲点
金属加工メーカーのA社では、慢性的な人手不足に加え、納期直前の受注が重なり、現場は一刻を争う状態でした。そんな中、ようやく派遣スタッフが初出勤の日を迎えます。
製造リーダーは「ボール盤なら比較的安全だし、操作も簡単なはず」と判断し、派遣スタッフに保護メガネと手袋を渡して、「とりあえず、こうやってみて。分からないことがあったら、近くの社員に聞いてね」と声をかけ、すぐに作業へ入ってもらいました。
「やって覚えるのが一番早い」――これは、長年現場で働いてきたリーダー自身の実感でもあり、過去にはうまくいっていたやり方でもあります。
ただ、スタッフ本人の経験値や危険認識が異なる中で、こうした対応は本当に適切だったのでしょうか?
特に、作業内容や設備の特性によっては、ちょっとした思い込みや説明の省略が、想像以上のリスクにつながる可能性もあります。
“慣れ”に頼らない安全教育のすすめ
言わなくなったけれど残っている、「見て覚える文化」のリスク
作業は見て覚えるもの。現場に入れば、自然と慣れていく――
そうした空気感は、かつて多くの製造現場で当たり前のようにあったかもしれません。
最近では明言されることは少なくなったものの、忙しい中で細かく説明できず、「とりあえずやってもらう」状況が、今も一部では起きているのではないでしょうか。
しかし、派遣スタッフは設備も職場のルールも初めて。
たとえ簡単な作業に見えても、前提となる知識や安全意識が異なる中での“自己流”は、想像以上のリスクを伴います。もし事故が起きれば、スタッフ本人だけでなく、現場の作業計画や企業の信頼、そして何よりも命に関わる問題へと発展しかねません。
だからこそ、派遣スタッフが安心して現場に立てるよう、事前の安全教育が不可欠です。
作業内容・使用機器・注意すべきポイントを明確に伝えることで、スタッフの安全意識を高め、職場全体のリスクも下げることができます。
フジアルテでは、各現場の特性に応じて事前説明を行い、必要に応じた補足教育や確認の機会も設けています。
「まず安全から入る」文化づくりを、派遣会社として企業様と共に進めていく――それが私たちのスタンスです。
📝ちょこっとメモ
“やればわかる”では、安全は伝わらない。
■例:
初日から現場に入り、見よう見まねで作業。事故発生時、「伝えたつもり」だったが、本人は理解していなかった。
→作業手順や注意点は紙・口頭・実演など複数の手段で伝える。特に初日の教育は「言ったか」ではなく「伝わったか」が重要。
“安全のつもり”がリスクになることも ― 保護具の選定ポイント
手袋=安全とは限らない。現場ごとのリスクとルールの再確認
安全衛生の観点から、保護具の着用は基本中の基本――これはどの企業様も徹底されていることかと思います。
ただし一方で、「全ての場面で保護具が安全を高める」とは限らないケースもある、というのが現場の難しさです。
たとえば、ボール盤のように回転体を扱う作業では、手袋の着用が逆に事故を引き起こす危険性があります。
刃先や回転部に引っかかって巻き込まれると、骨折や重大なけがにつながるおそれがあるため、法令でも着用が禁止されている作業があります。
こうした注意点は、製造業のご担当者であればすでにご存知の方も多いと思いますが、派遣スタッフがそのリスクを正しく認識しているとは限りません。「なぜこの保護具は必要なのか」「なぜこれは使ってはいけないのか」――その意味まで含めて共有できているかどうかが、安全確保の分かれ道となります。

保護具の適正使用については、派遣スタッフ自身が危険性を十分理解していないケースもあります。
そこで私たちも、就業前の説明時に工程ごとに特に注意が必要な点や、保護具の使用ルールについて、あらかじめ丁寧に共有するよう心がけています。
「安全の常識」は現場によっても少しずつ異なるもの。
だからこそ、派遣元と派遣先が事前にすり合わせを行うことで、認識のズレから生じる思わぬ事故を防ぐことができる――
それはこれまでの経験を通して、私たち自身が強く実感していることです。
📝ちょこっとメモ
保護具は“万能”ではない。状況に応じた使い分けが必要。
■例:
ボール盤作業で手袋着用 ⇒ 回転部に巻き込まれ、重大事故に。
→作業ごとに“使うべき保護具”と“使ってはいけない保護具”を明確化し、スタッフへの事前説明に含める。
“あるのに伝わらない”手順書の落とし穴
掲示して終わり、では事故は防げない。「使われる」仕組みへ
作業手順書の整備は、安全・品質・効率を支える土台――
製造現場でそうした取り組みが進んでいることは言うまでもありません。
とはいえ、「手順書はあるけれど、実際には見られていない」「そもそも存在すら知らなかった」という場面に出くわすことも、現場では珍しくありません。特に派遣スタッフのように初めて現場に入る方にとっては、明文化された“正しいやり方”がどこにあるのか、いつでも確認できるのかが極めて重要です。
また、慣れた社員同士の間では、効率や実績を重視するあまり、「こうした方が早いよ」「昔からこのやり方だった」という独自ルールが暗黙的に受け継がれていることもあります。
それが必ずしも間違っているとは言い切れませんが、こうした“現場の慣習”が、手順書との乖離を生み、結果として事故の温床になるケースも少なくありません。
私たちも現場での支援を通じて、「掲示物はあるのに読まれていなかった」「作業中に確認できる場所になかった」といった事例にたびたび直面してきました。
“あればよい”ではなく、“使われる手順書”にするには、配置場所や内容の分かりやすさ、実際の教育との連動が不可欠だと、あらためて感じています。
📝ちょこっとメモ
手順書は、“読まれる設計”でなければ意味がない。
■例:
作業台の近くに手順書がなく、記憶頼りの作業で手順を誤り事故に。
→見やすい場所への掲示、簡潔な図解、教育との連動で、“使われる手順書”へと改善。
“前任者からの引き継ぎ”がリスクを生むとき
現場に根づく“なんとなくのルール”が事故を招く
作業のやり方が前任者から口頭で伝えられ、それが「現場の常識」として定着していく――
製造現場では、こうした状況も少なくないのではないでしょうか。
スピード重視や、人手不足の中での最適化の結果として、正式な手順とは異なるやり方が自然と受け継がれてしまうケースがあります。
たとえば、ある組立現場でのケースです。
本来は部品の固定時に専用の治具を使うルールでしたが、固定に時間がかかるという理由から、社員の間で“手で押さえてそのまま固定する”というやり方が慣習化していました。
見た目には効率的で、日々の作業も支障なく進んでいたように見えましたが、ある日、作業中に部品がずれ、指を挟んでしまう事故が発生してしまいました。
現場では「そんなやり方、誰が教えたの?」という声が上がりましたが、実はそれが何年もかけて自然と広がっていた“なんとなくのルール”だったのです。

私たちも現場を訪問させていただく中で、こうした“明文化されていない慣習”が作業の前提になっているケースを目にすることがあります
本来の手順があっても、それが現場に根付いていなければ、安全は担保できません。
今のやり方は、本当に安全な前提に立っているのか――そんな視点を、定期的に現場で確認し合える環境づくりが、リスクを未然に防ぐ鍵になると考えています。
📝ちょこっとメモ
慣習化した“独自ルール”は、見直す機会を失いやすい。
■例:
治具を使わず手で固定する方法が、数年かけて慣例化 ⇒ 指挟み事故に発展。
→定期的な現場ヒアリングと安全巡回で、“正式な手順と現場実態のズレ”を把握し、対処する。
安全は“誰か任せ”にできない時代に
派遣元・派遣先でつくる「安全の共通認識」が未来を守る
派遣スタッフの受け入れにおいて、安全への備えは「現場の工夫」や「経験値」だけに委ねるものではなくなってきています。
製造現場の多様化、働く人の背景の変化――そうした時代の中で、あらためて「当たり前の安全」をどう実現するかが問われています。
特に、派遣スタッフは初めてその職場に立つ方が多く、周囲の“暗黙のルール”や“目配せ”だけでは、安全を担保しきれません。だからこそ、受け入れ前の準備段階で、派遣元・派遣先の双方が「安全の共通認識」を持つことが、最も基本であり、最も効果的な対策になるのではないでしょうか。
フジアルテでは、派遣先企業様の安全衛生活動と歩調を合わせながら、スタッフが安心して力を発揮できる現場づくりを今後も支えてまいります。
ご不安な点や「他社ではどうしている?」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報