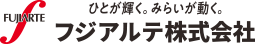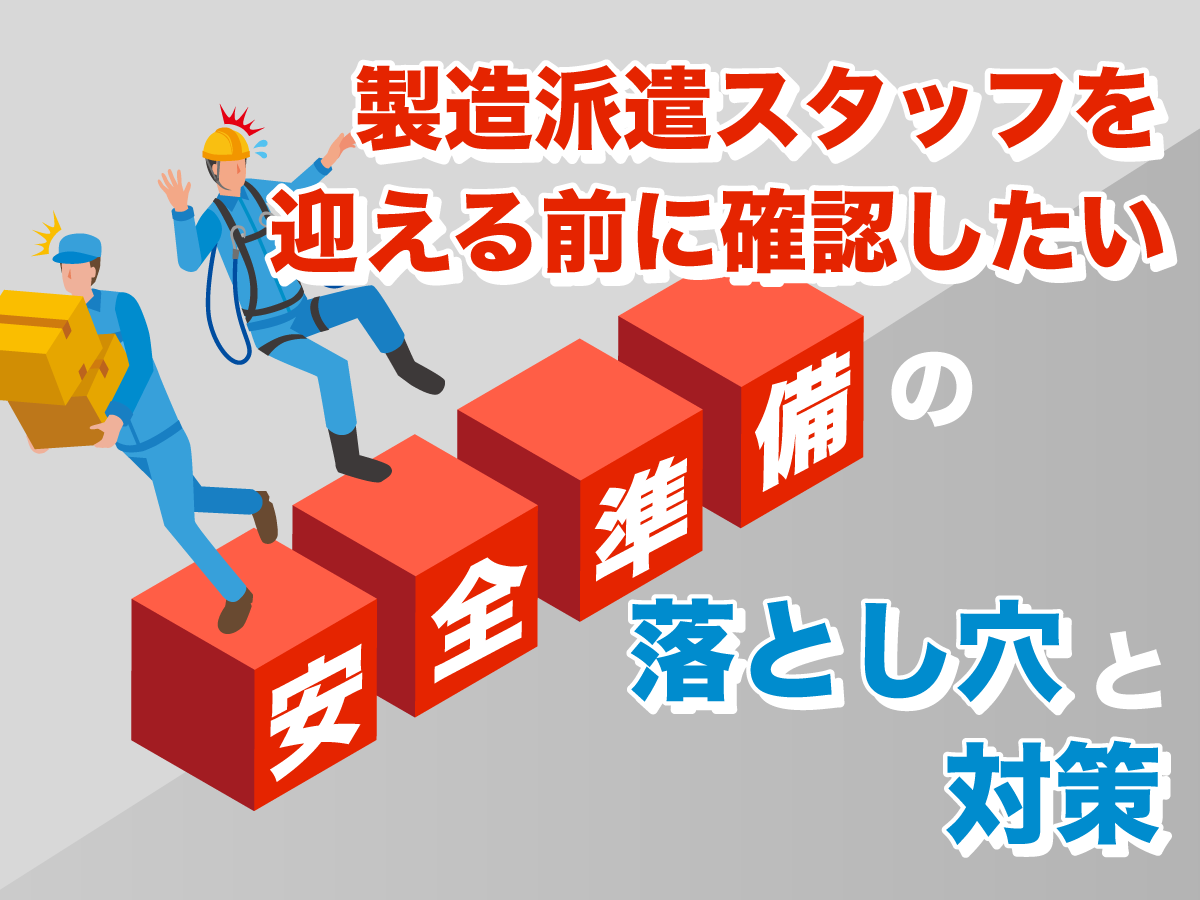派遣コラム
製造現場の安全管理、法律だけで十分? 派遣受け入れ時に注意すべき安全衛生法の落とし穴

Q.安全衛生法を守っていれば、派遣スタッフの安全は確保できるのでは?
A.安全衛生法は“最低限の基準”です。守っていても、実際の現場では事故が起きることがあります。
安全衛生法は労働災害を防ぐための大切な枠組みですが、
製造現場のすべての作業リスクを想定しているわけではありません。
とくに、化学薬品や機械設備を扱う環境では、法令上「問題なし」とされる条件下でも、健康被害のリスクが残るケースがあります。
私たち派遣会社は、法令遵守を前提に、“より安全な現場”を共に作るパートナーとして対応しています。
Table of Contents
事例:短時間の塗装工程で防護具を省略したケース
電子部品メーカーのC社では、製品の外装塗装に有機溶剤(トルエン等)を使用していました。
1回あたりの作業時間は15分程度と短く、社員の間では「この程度なら防毒マスクはいらない」という慣習がありました。
派遣スタッフの受け入れに際し、派遣元の営業担当が現場を確認したところ、
換気装置は設置されていたものの、防毒マスクの着用が徹底されていない状況が判明。
担当者は、作業環境測定の数値が基準内であっても吸入リスクが残るとして、
安全対策が整うまでは派遣を見合わせる判断をしました。
C社の人事担当者は「法律上問題がないのに、なぜ派遣できないのか」と疑問を抱きました。
法令遵守は“出発点”にすぎない
派遣元は、派遣スタッフの雇用主として安全配慮義務(労基法第5条・派遣法第44条)を負っています。安全衛生法を満たしていても、実際の環境で健康被害や災害のリスクがある場合、派遣元には派遣を控える・改善を依頼する責任があります。
安全衛生法第3条には、次のように定められています。
❝事業者は、この法律で定める最低基準を守るにとどまらず、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保するように努めなければならない。❞
つまり、安全衛生法は“守るべきライン”であり、実際の安全確保には企業同士の協力と運用レベルでの工夫が必要です。
よくある誤解とリスク
「短時間だから大丈夫」
作業時間が短くても、溶剤の揮発やガスの吸入によって頭痛・目の痛み・吐き気などの症状が出る場合があります。防護具をつけずに慣れてしまうと、慢性的な健康被害を引き起こすこともあります。
「法律に違反していない=安全」ではない
有機溶剤中毒予防規則などで定められた濃度基準を守っていても、
換気や防護具の使用が不十分な場合は、実際のリスクが残ります。
現場環境は日々変化します。作業内容・季節・人員によって危険の度合いも変わります。
派遣元としては、“測定値だけで安全と判断しない”ことを基本としています。
派遣元が大切にしている考え方
① 「法令遵守+実態確認」
派遣先での作業内容・使用物質・設備状況を必ず確認します。
法的には問題がなくても、作業環境や手順に改善の余地がある場合はご相談させていただきます。
② 「現場の方々と協働して安全をつくる」
派遣元だけでなく、派遣先のご担当者様・現場リーダーの皆様と
“どうすれば事故を未然に防げるか”を一緒に考えることを重視しています。
③ 「スタッフの安心=企業の信頼」
派遣スタッフが安心して働ける職場は、生産性や定着率にも直結します。
法令基準を超えた安全対策は、結果的に派遣先企業のリスクマネジメントにもつながります。
まとめ
安全衛生法を守ることは当然の責務です。
しかし、それだけで「安全な職場」とは言い切れません。
派遣会社が法令以上の安全対策をお願いするのは、
「現場で働く方の命を守る」ため、そして「貴社の安全文化を共に高める」ためです。
フジアルテは、派遣先企業の皆様と共に、“法令を超えた安心の職場づくり”を目指しています。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報