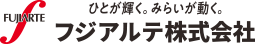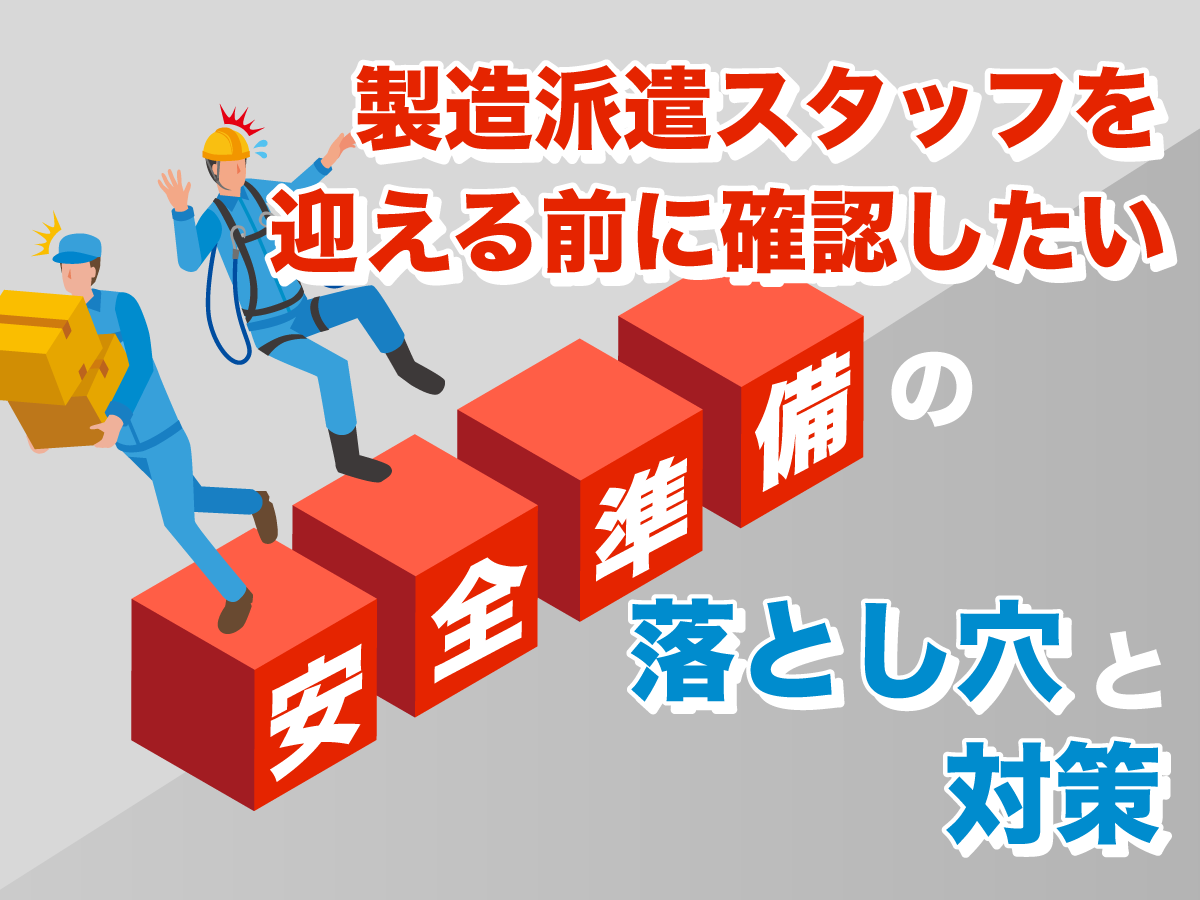派遣コラム
KYTが“意味ない”と感じる3つの理由と、すぐできる改善策

「KYTって、正直意味あるのかな…?」
そう感じたことはありませんか?
新人が理解できていない、毎回同じテーマで飽きられている、時間短縮ばかり意識している…。
本記事では、KYTが形骸化する3つの理由と、明日から実践できる改善策を紹介します。
Q.このコラムでは何が書かれているの?
A.「KYTって意味あるの?」と感じる現場に向けて、形骸化の原因と改善策を解説します。現場の声から生まれた、すぐ使える見直しポイントを紹介しています。
Q.このコラムで最も大事なポイントは?
KYTが“意味ない”のではなく、“伝わっていない”だけかもしれない。少しの工夫で、KYTは現場を動かす力に変わります。
Table of Contents
KYTが“意味ない”と感じられる3つの原因
(1)新人・外国人スタッフに「KYTの目的」が伝わっていない
現場に配属されたばかりの新入社員や外国人スタッフにとって、「KYT」は“見よう見まねでなんとなく参加する時間”になっていませんか?
例えば、「危険予知」と言われても、その背景にある“なぜそれが大切か”という目的が伝わっていなければ、単なる形式としてしか受け取られません。
実際、「事故なんて自分には関係ない」と無意識に思っている新人ほど、KYTで話される事例や注意喚起が他人事になってしまいがちです。
また、外国人スタッフの場合、専門用語や作業手順に関する背景知識が十分でないまま参加することも多く、「分からない」「言いにくい」と感じているケースもあります。
KYTの目的は、「誰かのために」ではなく、「自分自身が怪我をしないための訓練」。
この認識が共有されていなければ、いくら正しい手順で実施しても“意味が伝わらない”状態になってしまいます。
【📝ちょこっとメモ】
KYTの目的は「自分と仲間を守ること」。まずはその意味を“わかりやすく伝える”仕組みづくりから。
例:
配属初日の新人が「怪我なんて、自分にはまだ関係ないです」とつぶやいた。背景を知らず、他人事になっていた。
→ KYT開始前に「なぜ行うのか」を新人向けに動画・事故事例で説明。チームメンバー全員で“目的の共通理解”を意識づけ。
(2)テーマが現場の実態とかけ離れている
KYTでは、事故や災害の事例、作業シーンのイラストをもとに危険を予測します。
しかし、いつも同じようなイラストや、現場とは無関係のケースを繰り返し取り上げていては、「うちには関係ない」と感じる人が出てきます。
例えば、
- 実際のライン作業とは全く違う工程のイラスト
- 年に一度しか発生しないようなレアケース
- 作業者がイメージしづらい古い災害事例
このようなテーマでは、危険を“自分ごと”として捉えるのが難しく、反応も形式的になりがちです。
リアリティのあるテーマとは、日々のヒヤリハット、直近のライン変更、5S活動での気づきなど、実際の現場と地続きになっているものです。
現場に即したテーマ選びが、KYTの効果を引き出すカギになります。
【📝ちょこっとメモ】
KYTのテーマが現場とかけ離れていたら、いくら訓練しても心には響かない。
例:
「このイラスト、フォークリフトなんてないじゃん…」と小声で漏らす作業者。実際の職場と結びつかないテーマでは共感が得られない。
→ 日常のヒヤリ・5S改善報告・設備変更など、“現場で今起きていること”をテーマ候補に反映。現場とつながる素材で共感を喚起。
(3)進め方がマンネリ化し、「やらされ感」が漂っている
「KYTやります」「はい、じゃあいつものようにこのシートを見て…」
そんな一言から始まるKYT、思い当たりませんか?
進行役が毎回同じ、発言者も限られている、テーマも固定…。
このような“マンネリ化”は、KYT本来の価値を感じにくくさせ、参加者の集中力や発言意欲を削いでしまいます。
とくに、「どうせこういう結論になるだろう」と最初からゴールが見えている進行は、経験者ほど飽きを感じやすくなります。
少しの変化で空気が変わることもあります。
例えば:
- 進行役を交代制にしてみる
- チーム編成や発言順を変えてみる
- 写真や動画を使って五感に訴える
こうした工夫によって、“やらされるKYT”から、“自分たちで考えるKYT”への転換が期待できます。
【📝ちょこっとメモ】
小さな変化で、KYTは“作業”から“対話”に変わる。
例:
「どうせ“安全確認ヨシ!”って言うだけでしょ」と話すベテラン社員。発言者も内容も固定され、形だけの参加に。
→ 進行役や発言順をシャッフル。写真や動画を使った五感刺激、クイズ形式などで“参加したくなるKYT”へ雰囲気を刷新。
「やってよかったKYT」に変える3つの工夫
(1)目的共有のタイミングを、KYTの“前”に仕込む
KYTは始まった瞬間に効果が決まるわけではありません。
特に新人・外国人スタッフに対しては、事前に「なぜやるのか?」を理解してもらう導入のひと工夫が有効です。
例えば、配属時に「過去に実際に起きた災害事例」や「作業中に発生したヒヤリハット動画」などを使い、“自分にも起こり得るリスク”を実感させた上でKYTに参加してもらうことで、意識の入り方がまったく違ってきます。
また、言語面で不安のある外国人スタッフには、イラスト・動画・母国語翻訳などを活用し、安心して参加できる空気づくりが効果的です。
【📝ちょこっとメモ】
「目的は最後にまとめて言う」よりも、「最初に体感させる」ほうが伝わる。
例:
「KYTって、ああいう事故を防ぐためなんですね」と新人が言葉にした瞬間、チーム内の空気も変わった。
→ 配属初期に“意味づけ”を入れた動画視聴と、上司のひと言でKYTへの姿勢が前向きに。
(2)テーマを“今の現場”から拾う仕組みをつくる
テーマの選定は、現場に寄り添うKYTを実現するうえで最重要ポイントの一つです。
過去の災害事例やテンプレシートだけに頼るのではなく、 日々のヒヤリ・設備変更・5S改善記録など、現場に“いま”起きていることを素材にしてみましょう。
たとえば、
• 工場巡視で指摘された“物の置き方”
• 改造した台車の使用開始日
• ピッキング手順の変更直後
…こうした“ちょっとした変化”もテーマに取り入れることで、「うちの現場に合ってる」と実感しやすくなります。
【📝ちょこっとメモ】
テーマの質は「情報源の質」で決まる。KYTは現場から学べる仕組みに。
例:
台車のキャスター変更初日、KYTで「傾斜で滑るリスク」に全員が気づけた。
→ 現場変更とKYTを連動させる仕組みにより、ヒヤリ予防に直結。
(3)進行に“ちょっとした変化”を加えるだけで空気が変わる
KYTは定例活動になりがちですが、それゆえにちょっとした変化が新鮮さを生みます。
進行役をチームでローテーションしたり、発言の順番をランダムにしたりするだけでも、参加意識が大きく変わります。
また、写真を使った「間違い探し」や、ベテラン社員の「私のヒヤリ体験」をテーマにした回など、メンバーが“引き込まれる仕掛け”も有効です。
KYTの目的は、「正解を言う」ことではなく、「考える力を育てる」こと。
だからこそ、進行役の一声や雰囲気づくりが、その場の価値を左右します。
【📝ひとことメモ】
K=危険、Y=予知、T=“退屈”じゃない。仕掛け次第でKYTは変えられる。
例:
「この写真、何かおかしいところある?」と進行役がクイズ形式でスタート。
→ 最初の笑いが緊張を和らげ、KYTの意見も活発に。
「やるべき」は「伝わる」に変えられる。フジアルテの安全教育
「やった方がいいこと」と「現場で伝わること」は、必ずしも一致しません。
KYTのような安全教育は、「言ったつもり」「理解したつもり」になりがちだからこそ、“伝え方”と“タイミング”の工夫が重要です。
フジアルテでは、現場配属前の雇入時安全教育において、
以下のような“伝わる工夫”を事前段階から取り組んでいます。
- 業務中・通勤中の災害事例をイラスト付きで説明
- 構内ルールや設備の特徴を写真や動画でわかりやすく提示
- 外国人スタッフには母国語支援と視覚教材を活用
また、配属後も定期的に現場のヒヤリングを実施し、KYTや5S活動と連動する形で“現場の声”を安全支援に反映しています。
さらに、当社の管理担当者は全員、「職長教育」を受講済み。
お客様の現場で実施されるKYTや安全活動に対しても、共通言語で理解し、伴走できる体制を整えています。
「意味がない」と感じたら、“やり方”を見直すチャンスです
KYTは、安全教育の中でもっとも「形骸化しやすい」取り組みの一つかもしれません。
けれど裏を返せば、ちょっとしたやり方の工夫で“大きな差”が生まれる訓練でもあります。
- なぜKYTをやるのか、その意味が伝わっているか
- 現場にフィットしたテーマが選ばれているか
- 参加者の意識を引き出す仕掛けがあるか
この3点を見直すだけでも、「KYTは意味がある」と実感できる現場に変えていけます。
「意味がない」と感じるのは、現場が変化している証拠です。
だからこそ、やり方もアップデートするタイミングなのかもしれません。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報