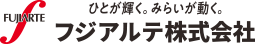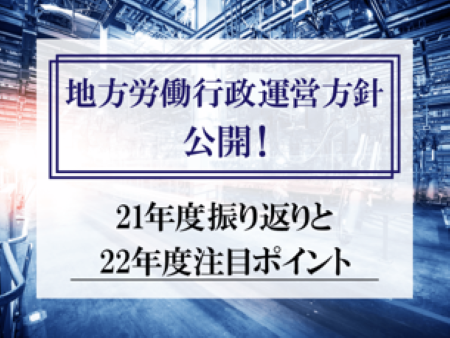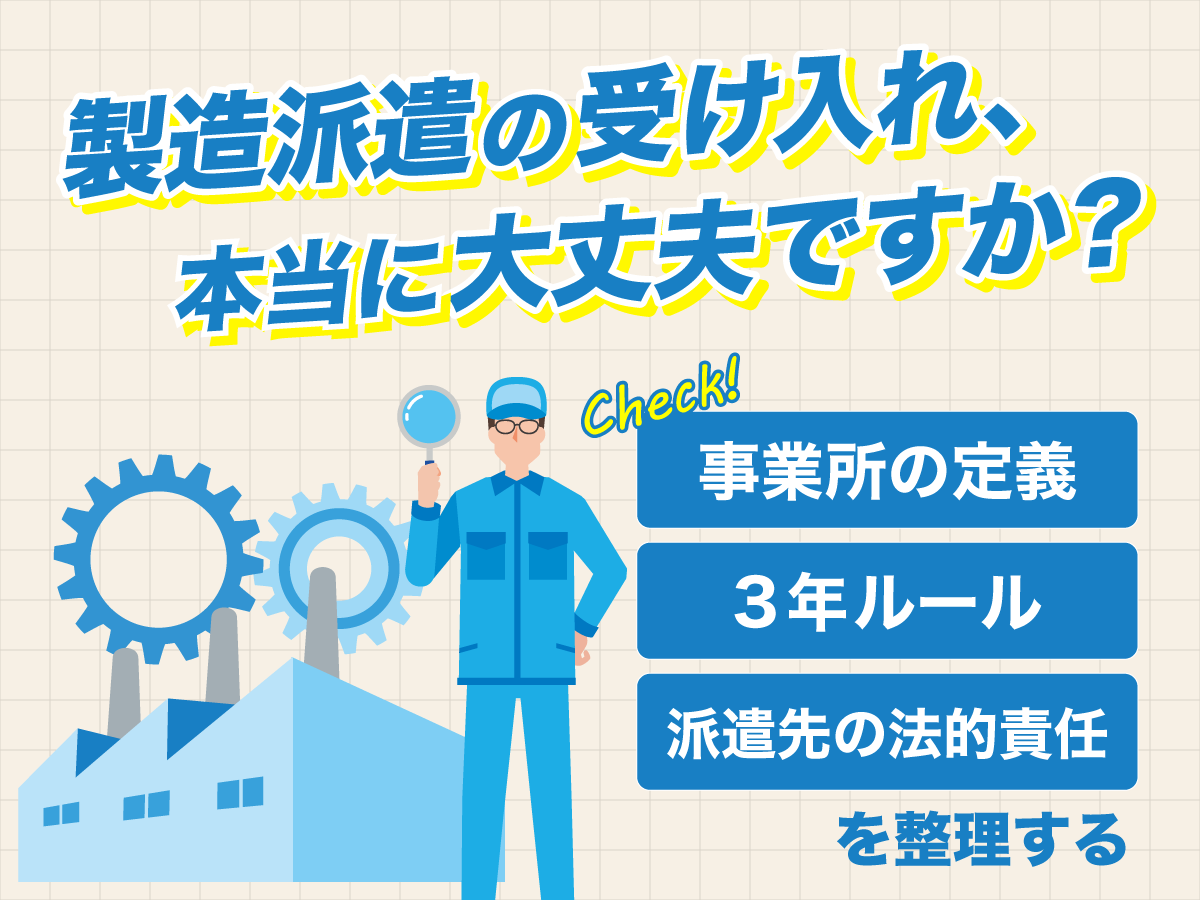派遣コラム
『残業お願いしても大丈夫?』派遣先企業が誤解しやすい勤務時間ルール
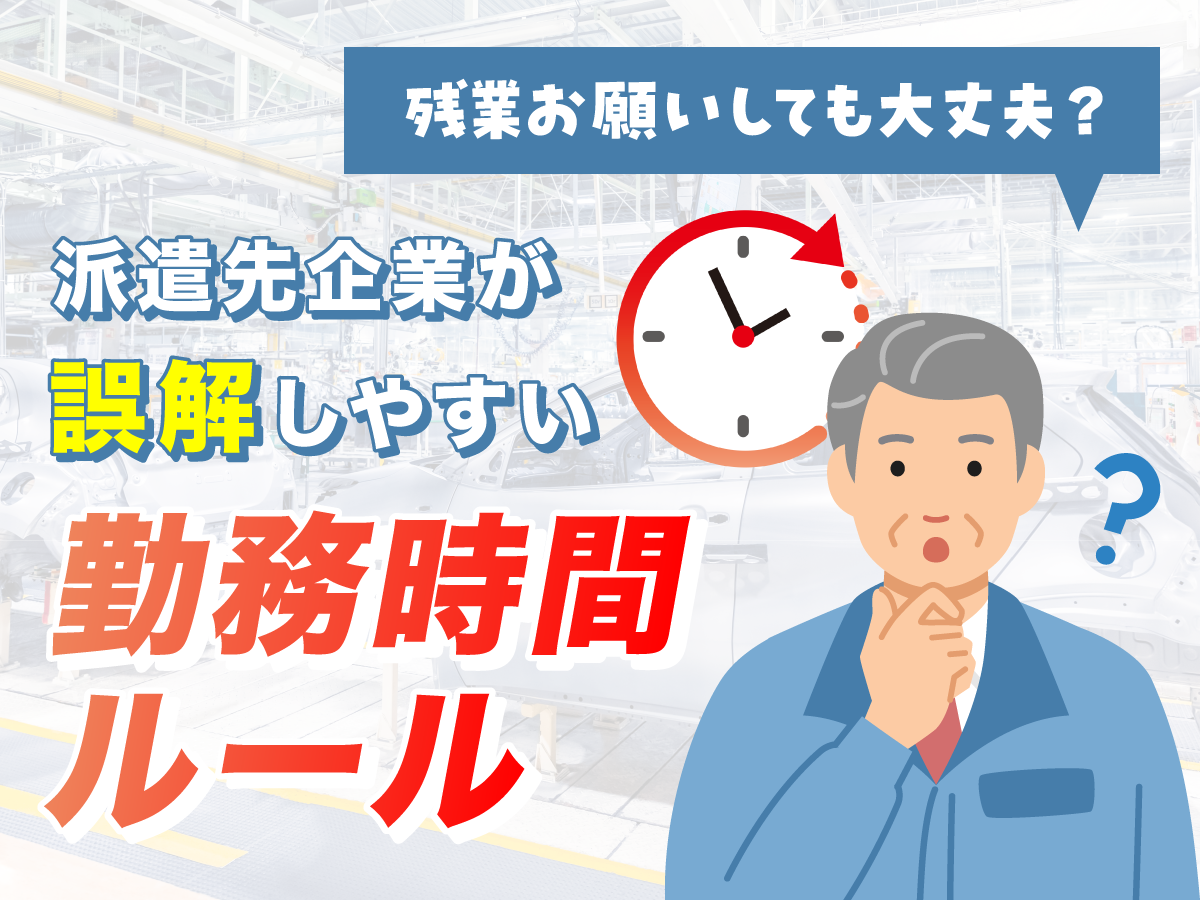
Q.派遣スタッフの勤務形態や残業時間は、派遣先企業が自由に決められるのですか?
A.いいえ。派遣先企業だけで自由に決めることはできません。
派遣スタッフの労働条件は、雇用主である派遣元(派遣会社)との契約内容に基づいています。
したがって、勤務時間・残業・休日労働・夜勤などを変更する場合は、派遣元との確認と合意が必要です。
また、時間外・休日労働をさせる場合は、派遣元が労使協定(いわゆる「36協定」)を締結していることが前提となります。
派遣先はその範囲内でのみ、残業や勤務形態の変更を依頼できます。
結論として、派遣先が一方的に残業やシフトを決めることはできず、派遣元との連携・契約確認が不可欠です。
Table of Contents
事例
事例1:急な増産で夜勤シフトを検討するC社
自動車部品メーカーのC社では、主要取引先からの急な増産要請を受け、生産ラインを夜間まで拡大する必要が生じました。
もともと派遣スタッフは「日勤専属(8:00〜17:00)」として契約していましたが、C社は派遣会社に対して
「夜勤(17:00〜翌1:00)や残業をお願いできないか」と相談しています。
しかし人事担当者の頭をよぎったのは次のような疑問です。
- 夜勤や残業を依頼しても、契約や法律に違反しないか?
- 派遣元の36協定の範囲を超えないか?
- 派遣先として、どこまで責任を負う必要があるのか?
事例2:繁忙期に変形労働時間制を導入しているD社
精密機器メーカーのD社では、毎年12月〜2月の繁忙期に合わせて「1日10時間勤務の変形労働時間制」を採用しています。
同じ期間に派遣スタッフを利用したいと考えていますが、
「自社の制度に合わせて派遣スタッフにも同じシフトを組めるのか?」
「変形労働時間制を派遣契約にどう反映すべきか?」
といった判断に迷っています。
派遣先が勤務時間を決める際の3つの原則
① 契約内容の範囲を超えた勤務変更はできない
派遣スタッフの勤務形態や時間は、派遣元との「派遣契約書」および「就業条件明示書」に明記されています。
契約上「日勤のみ」「残業なし」とされている場合、派遣先が一方的に夜勤や残業を指示することはできません。
まずは、派遣元の36協定(時間外・休日労働に関する協定)と、契約書上の勤務条件を確認することが重要です。
派遣元が36協定を締結していない場合、そもそも残業や休日出勤をさせること自体が違法になります。
② 残業・休日出勤は派遣元の36協定の範囲内で
派遣スタッフに法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超えて働いてもらう場合、
派遣元が36協定を締結・届出していることが前提です。
通常、1か月あたりの残業上限は45時間、年間360時間が原則ですが、
「特別条項付き36協定」を結んでいれば、繁忙期などに年720時間まで延長できる場合もあります。
ただし、この特別条項を使う場合は、
- 一時的・臨時的な事情に限ること
- 労使間の手続き・通知が必要なこと
- 健康管理・過重労働防止措置を取ること
などの条件が課せられています。
派遣先としては、派遣元の36協定内容を確認し、その範囲内で残業を依頼することが求められます。
③ 派遣先にも「使用者的責任」がある
派遣スタッフの労働時間や休憩、休日の管理は、派遣先にも「使用者的責任」があります(労働者派遣法第44条2項)。
つまり、派遣先は指示した勤務時間や残業について、実際の始業・終業時刻を把握し、派遣元に報告する義務があります。
C社のように夜勤シフトを導入する場合も、健康管理や深夜割増賃金など、安全衛生面も含めて派遣元と十分に協議することが重要です。
変形労働時間制を適用する際の注意点
D社のように繁忙期のみ10時間勤務を行うなど、変形労働時間制を派遣スタッフに適用したい場合、
派遣元が変形労働時間制の労使協定を締結していることが前提となります。
- 1か月単位の変形労働時間制であれば、就業規則への記載で対応可能
- 1年単位の変形労働時間制は、派遣元と労使協定が必要
ただし、派遣契約は通常3か月や6か月といった短期間で締結されるため、
「1年単位の変形労働時間制」との整合が取れないケースが多くなります。
その場合は、原則1日8時間勤務+36協定範囲内での残業が基本です。
特別条項・変形労働制を適用する目的が妥当か
36協定の特別条項は「臨時的な特別の事情」に限られます。
恒常的な人手不足や慢性的な残業を正当化するために使うことはできません。
一方、変形労働時間制は、繁閑の差を前提にあらかじめ労働時間を配分する制度であり、
「常に残業が発生している職場」には本来なじみません。
C社やD社のように、繁忙期のみ人員を強化したい場合は、
制度の趣旨を踏まえ、派遣元と協議のうえで適切な運用を行うことが必要です。
勤務時間に含まれる「見落としがちな時間」
作業前の待機時間や業務説明、準備体操、朝礼・終礼などが定例的に行われている場合は、
すべて勤務時間に含まれます。
これらを「無給」として扱うと、未払い賃金の問題になるため注意が必要です。
まとめ
派遣スタッフの勤務形態や残業は、派遣先だけで決められるものではありません。
契約上の定め、派遣元の36協定、労働基準法・派遣法に基づく制限の中で、
派遣元と派遣先が連携して調整することが前提です。
繁忙期や交代制勤務のような柔軟な働き方を導入する際も、
「契約の範囲」「健康管理」「労使協定」の3点を必ず確認しましょう。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報