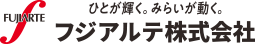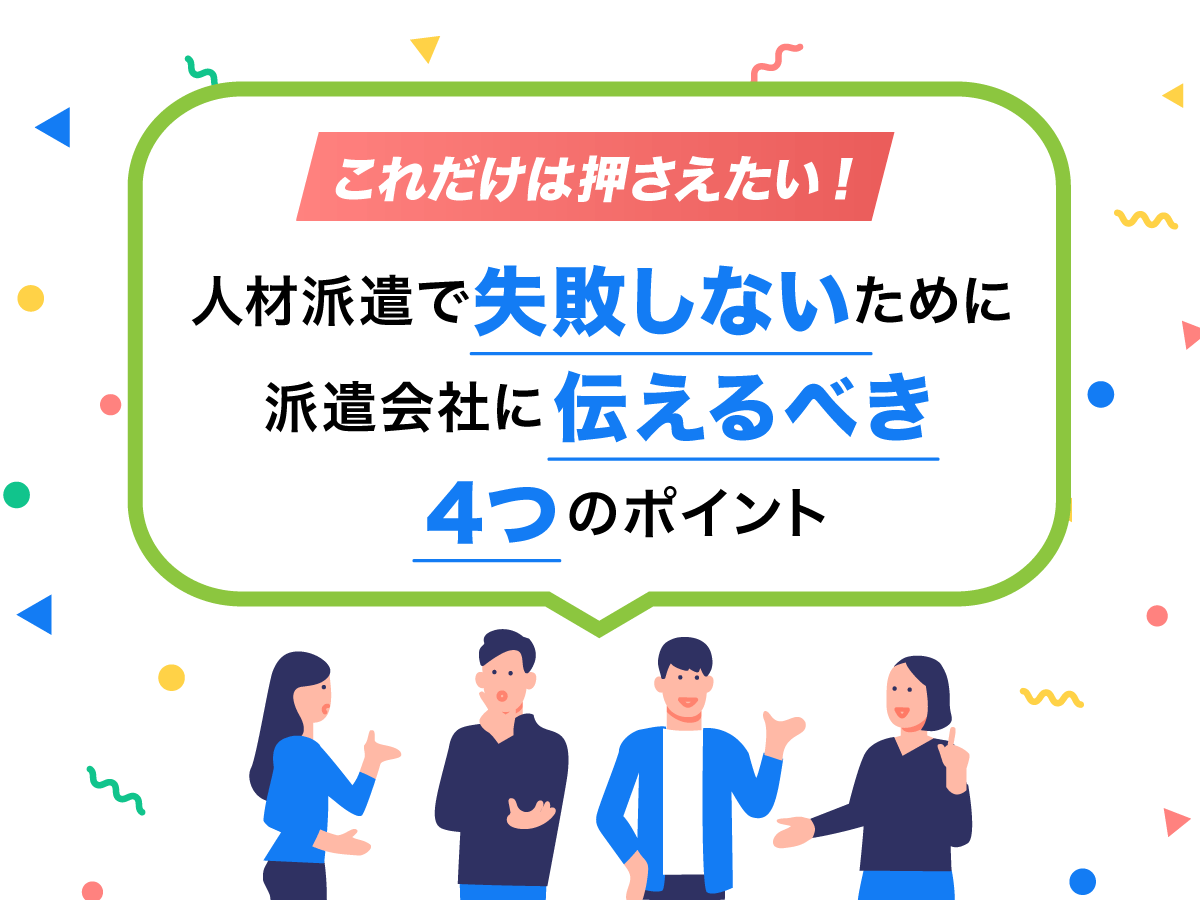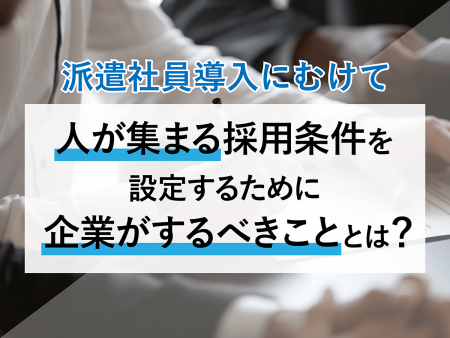派遣コラム
「それ、選考になっていませんか?」派遣スタッフの“特定行為”とミスマッチを防ぐ職場見学の活用法
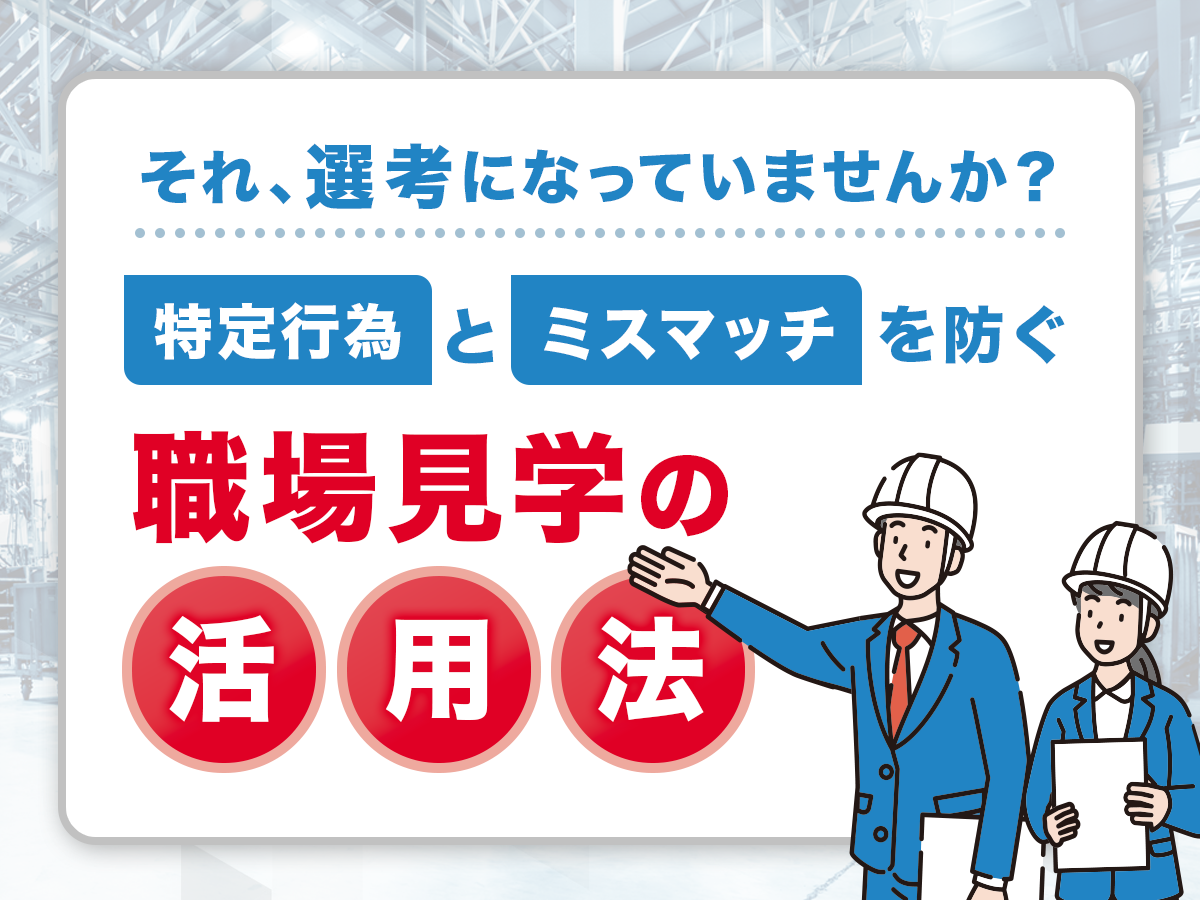
派遣スタッフが実際に配属されたあと、「こんなはずじゃなかった」「この作業は無理かもしれない」と早期に退職してしまうケースは、現場にとっても派遣元にとっても大きなロスになります。
その背景には、「派遣先がスタッフを選んではいけない」という派遣法上のルールと、「現場に合う人材に来てほしい」という実務上のニーズとのギャップがあります。
本記事では、派遣法上の「特定行為」の禁止事項と、ミスマッチを防ぐための職場見学の活用法について、具体例を交えて解説します。
例|機械部品メーカーA社
ある機械部品メーカーA社では、現場作業の人手不足により、初めて製造派遣の導入を決定しました。
実際の工程を見てもらいたいという意図から、派遣会社の営業担当が派遣予定スタッフを現場に同行させることに。
現場責任者のフジ課長は、スタッフにこう声をかけました。
「それで、志望動機は? 過去にはどんな作業をやっていたの?」
「なるほど、じゃあ結果は後日、営業さんからお伝えしますね」
すると見学を終えて数分後、営業担当が戻ってきてこう言いました。
「フジ課長、すみません。お伝えしていたと思うのですが、面接や選定行為はできないんです。今回は職場を見てもらう目的の見学でしたので……」
フジ課長は不満げに返します。
「いやいや、うちは初めての派遣なんですよ? どんな人が来るかも分からず現場に入れるのは怖いでしょ」
このように、派遣法のルールと“現場の感覚”にはズレがあることが多く、知らず知らずのうちに違法行為に該当してしまうケースが後を絶ちません。
Table of Contents
派遣先がスタッフを“選ぶ”のはNG? 派遣法で禁止されている選定行為とは
「どんな人が来るのか事前に確認したい」――
これは派遣スタッフを受け入れる側であれば当然の思いでしょう。
しかし、その“確認”の仕方によっては、派遣法で禁じられている「選定行為」にあたる可能性があります。
派遣スタッフの受け入れにあたって、企業がどこまで関与してよいのか。その線引きを理解することは、コンプライアンス上だけでなく、長期的な人材パートナーシップを築く上でも欠かせません。
まず派遣法では次のように、派遣先が派遣社員を特定することを禁止しています。
また、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では派遣会社は派遣先企業が派遣スタッフを特定することに協力してはならないとされています
ここで言う「派遣スタッフを特定する行為」とは
① 派遣に先立って面接すること
② 派遣会社に対して派遣スタッフの履歴書の送付を依頼すること
③ 年齢条件を付けること
などを言います。
その他、面接と捉えられかねない発言・質問の例としては次のようなものがあります。
1 「前職ではどんな工場で働いていたの?」
※業務説明の範囲を超えて、職歴を評価していると取られる可能性あり
2 「うちの作業スピードについてこれそうですか?」
※適性の判断を現場で行っている印象を与える
3 「体力はある方ですか?続けられそうですか?」
※職場側が選別しているように聞こえる恐れあり
4 「今まで一番長く続いた仕事はどれくらい?」
※継続性や人柄を試す面接的な印象を与える
5 「今回は女性の方の方が合いそうなんですよね」
※性別条件を示唆する差別的選定と受け取られるリスクあり
6 「近くに住んでるんですか?通勤手段は?」
※通勤可否で選別しようとしていると誤解される恐れあり
7 「では、こちらで検討して、またご連絡します」
※選考の意思表示と捉えられる表現
1から6の質問は 能力や適正に関係のない項目です
7は派遣先企業が選考しているとの誤解を与える質問です
この他、思想、信条、宗教など各個人の自由であるべき項目についても質問することは避けた方が良いでしょう。
この事例では、一般的に面接で聞かれる志望動機をたずねたり、「結果は後ほどご連絡します」という派遣先企業が決定権を持つと解釈できる発言が該当します。
なぜ“選考”が問題になるのか? 派遣法が定める雇用関係の原則
派遣スタッフを選ぶ行為がなぜ問題になるのか――
それは、派遣という働き方の仕組みそのものに関係しています。
派遣スタッフは、「雇用主=派遣会社」「指揮命令を出す相手=派遣先企業」というように、雇用関係と現場の指示関係が分かれているのが大前提です。ところが、派遣先企業が面接を行って誰を受け入れるかを決めてしまうと、「雇用主のように選考している」とみなされるおそれがあります。この場合、派遣先が雇用主と判断されてしまうリスクがあり、トラブル時の責任の所在があいまいになってしまいます。
派遣契約は「この人に来てほしい」と個人を指名する契約ではありません。
あくまで「〇〇のスキルを持った人材を派遣してほしい」という契約であり、その人選は派遣会社が行うルールになっています。
この原則を守らなければ、法令違反だけでなく、信頼関係の破綻にもつながりかねません。
“選べない”ならどうする?ミスマッチを防ぐための派遣活用の工夫
とはいえ、派遣されたスタッフが実際に業務に対応できないような状況では、現場としても困ってしまいます。
「人を選べない」と言われても、現場に合わない人材を受け入れ続けるわけにはいかないというのが正直なところではないでしょうか。
そのためにはまず、依頼したい業務内容や作業環境を、派遣会社にどれだけ正確に伝えられるかが重要になります。
しかし実際には、「口ではうまく説明できない」「文章にすると伝わらない」といった声も多く、特に製造現場では、音・動き・温度・においなどの“空気感”が文字では伝わりにくいことも事実です。
そのような背景から、まずは営業担当者に現場を見に来てほしいというご要望をいただくことも少なくありません。
現地で直接工程を見ながら話すことで、派遣会社側も職場環境や作業の特性をより正確に把握でき、ミスマッチのリスクを大きく減らすことができます。
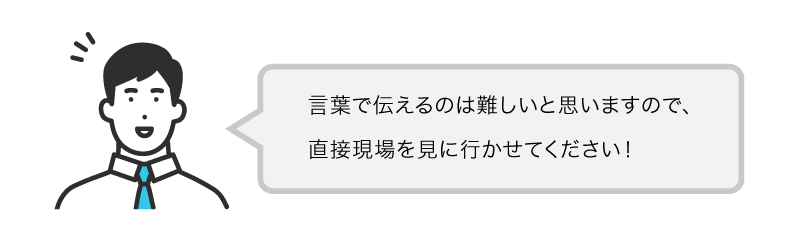
また、派遣スタッフ本人が事前に職場を見学することで、「自分にできそうかどうか」を判断する機会を持つことも、定着率向上において有効です。
職場見学で確認すべき8つのチェックポイント【現場視点で解説】
実際に職場見学を行う際には、派遣スタッフ本人が「この職場で継続して働けそうか」を判断できるよう、以下のような点を確認しておくことが重要です。
➢ 作業環境の雰囲気
例:工場内の騒音レベル、作業者のスピード感、空調環境など
➢ 業務内容の具体性
例:立ち作業か・座り作業か、重量物の取り扱いはあるか、検査・組立などの手作業の細かさ
➢ 作業時間と休憩の取り方
例:休憩場所やタイミング、連続作業時間の長さなど
➢ 人間関係や指揮命令の雰囲気
例:職場の方の話し方や空気感、外国籍スタッフの比率なども判断材料になることも
➢ 身体的な負荷や作業姿勢
例:前かがみ姿勢が多い作業、立ち作業の時間が長い工程など、体力面への影響
➢ 音・匂い・温度といった感覚的な要素
例:プレス機などの大きな音や油の匂い、夏場の温度感など、文章では伝わりづらい現場特有の感覚
➢ 作業リズムやラインスピード
例:単独作業かライン作業か、流れ作業のテンポが速いかどうかといった作業のペース
➢ 受け入れ体制の有無や教育方法
例:誰が初日の対応をするのか、指導の丁寧さなど、初日から安心して作業できるかどうか
これらを実際に“見て・感じて”もらうことで、「入社したら想像と違った」という事態を減らすことができます。
また、派遣会社側も見学内容をフィードバックとして受け取り、次回以降のマッチング精度を高める材料にすることが可能になります。
法令順守と定着率アップの両立をめざして
派遣スタッフの特定は禁止されている一方で、職場に合った人材を受け入れたいという思いもまた当然のことです。
法令を順守しながら、スタッフと現場のミスマッチを防ぐためには、「職場の情報を正確に伝えること」そして「スタッフが働くイメージを持てる環境を整えること」が何より大切です。
フジアルテでは、派遣先企業の状況を正確に理解し、スタッフにも納得感を持って就業いただけるよう、職場見学の支援やヒアリングを丁寧に行っています。
派遣後の定着率向上を目指すパートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報