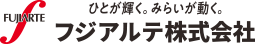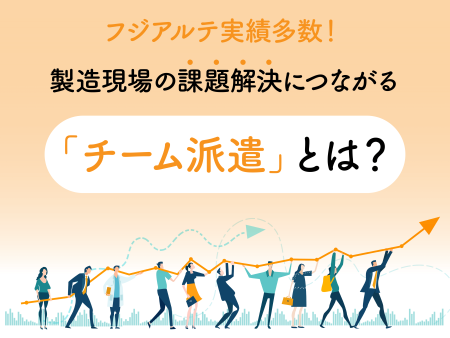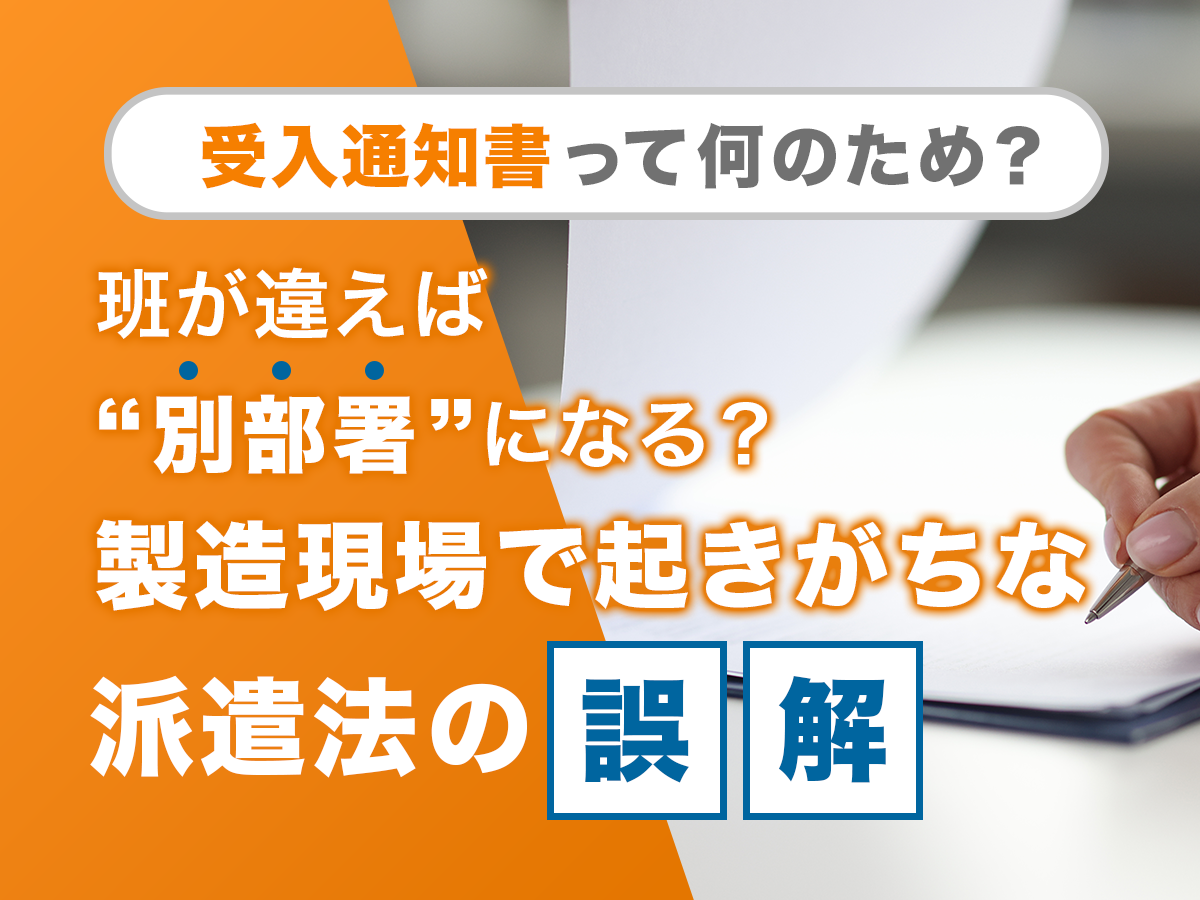派遣コラム
製造派遣 発注時に注意すべき内容は?
― 契約形態・3年ルール・みなし雇用のチェックポイント ―
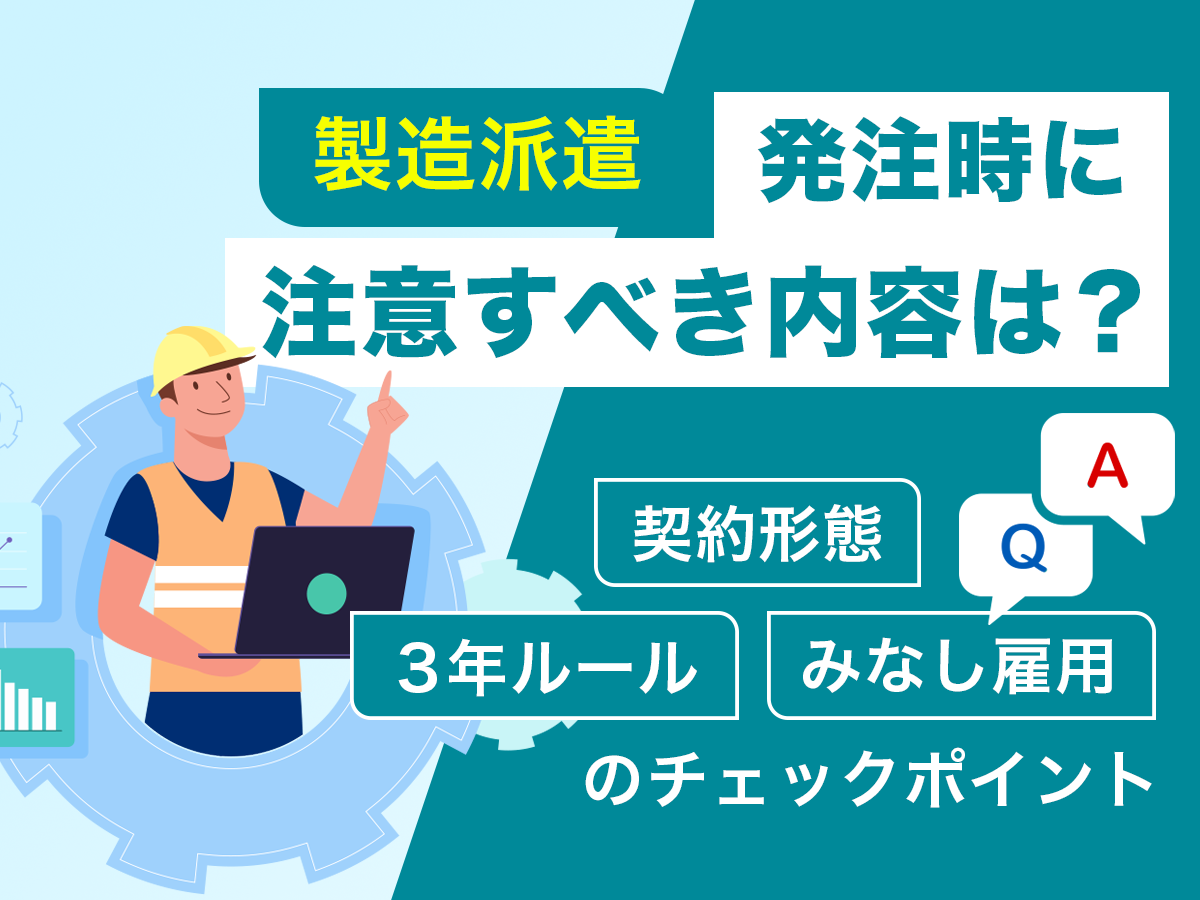
Table of Contents
お客様事例&はじめに
事例:自動車部品メーカーB社での製造派遣活用
B社では、四半期ごとの生産計画が直前まで流動的で、いつでもラインを止めずに回転させ続ける必要がありました。そこで有期契約の派遣スタッフを組み立て部門に配属し、急な増産時には即応できる体制を整えていました。
しかしあるとき、組み立て部門の3年超過スタッフを他部署へローテーションしたつもりが、実態は同じラインでの配属継続とみなされ、労働局から是正勧告を受けてしまいます。加えて「3年ルール」や「みなし雇用」の仕組みを知らなかったため、急遽発生した人件費増と行政対応に追われることになったのです。
このように、製造派遣の「発注前」に知っておくべきポイントを押さえておかないと、思わぬコスト増大や法令違反リスクに直面します。本記事では、契約形態の選び方から3年ルール、みなし雇用、さらには是正勧告リスクまで、Q&A形式でわかりやすく解説します。
契約形態の選び方
Q. 雇用型派遣・請負・紹介予定派遣、何を選べば安心?
A. 自社の繁閑や定着ニーズに合わせてメリット・リスクを比較して決めるのが安心です。
製造ラインのスポット的増員には雇用型派遣が適していますが、3年ルールの制約が強く、更新や手続きミスに注意が必要です。工程単位で成果を委託する業務請負は管理負担を軽減しますが、偽装請負にならないよう責任範囲を明確化しなければなりません。請負として扱う場合は、工程区分や責任範囲を明確にし、請負業務ごとに管理体制を整えましょう。
紹介予定派遣は、派遣終了後の直接雇用を前提とした仕組みです。採用リスクの低減や定着率向上が期待できますが、教育コストや評価手続きが増加します。採用予算や人事リソースと照らし合わせ、自社の中長期人材戦略に適合するかを検討して選択しましょう。
3年ルール(同一部署で3年超過すると違反!)
Q. 同一部署で3年超えると何がまずい?
A. “同一部署”で3年を超えると期間制限違反となり、行政指導や罰則の対象になります。
労働者派遣法では、同じ業務内容や指揮命令系統の下での就業を3年までに制限しています。ここでの「同一部署」とは、部署名や見かけではなく、業務内容・作業場所・指揮命令系統が同一かどうかで判断されます。たとえ部署名を変えても実態が同じであれば違反です。B社の事例も、まさにこの「実態ベースの判断」を知らなかったことが原因でした。
回避策としては、工程やラインをまたいで担当リーダーを切り替えるなど、運用レベルでの“実態切り分け”が必要です。また、配属日・異動日を正確に記録し、抵触日の6カ月前には次の対応(契約終了や別部署への配転)を決定するアラート設定を行うことで、違反を未然に防げます。
みなし雇用(3年超過で自動的に「雇用申し込み」扱いに)
Q. みなし雇用って誰が雇用される?
A. 3年を超えて同一部署で働く派遣社員は「申し込み義務」をしたとみなされ、派遣先の従業員となります。
労働者派遣法第40条の4により、同一部署で継続3年以上就業した派遣労働者は、派遣先が雇用を申し込んだものとみなされ、労働契約が成立した扱いになります。これにより、派遣先は社会保険料の事業主負担増加だけでなく、賞与や通勤手当などの各種手当支給、就業規則適用など全ての従業員管理責任を追うことになります。
この“自動雇用”が発生すると、年度末や年始に一気にコストが膨らみ、予算計画を大きく狂わせる恐れがあります。抵触日を契約書に明記し、定期的に契約更新時のチェックを実施、さらに人事・法務・現場を横断するレビュー体制を構築することで、みなし雇用のリスクを早期に察知し、適切な対応が可能になります。
条文引用:労働者派遣法 第40条の4(雇用の申込み義務)
派遣先事業主は、同一の組織単位において、三年以上継続して当該派遣労働者を就業させた場合には、当該派遣労働者に対し雇用の申込みを行ったものとみなす。
違反時のペナルティ(過料・行政公表・取引停止リスク)
Q. ルール違反すると具体的にどうなる?
A. 是正勧告にとどまらず、過料(罰金)や公表リスク、最悪の場合取引停止につながります。
法令違反が判明すると、まず労働局から是正勧告が発出され、改善計画の提出が求められます。これに応じない場合や対応が不十分と判断されると、数十万~数百万円の過料命令が科されることがあります。さらに、企業名が労働局ウェブサイトで公表されることで社会的信用を失い、大手取引先からの発注停止や金融機関の融資条件見直しといった二次被害を招くケースも見受けられます。
実際に、同一部署制限超過で過料50万円を科されたA社は、是正措置の公表をきっかけに主要顧客からの発注が3カ月停止され、結果的に数千万円の売上機会を逸失した事例があります。これを防ぐためにも、日頃からの運用チェックと現場担当者への周知徹底が欠かせません。
よくある質問
Q1. 契約形態は途中で変更できますか?
A. 可能ですが、新規契約の締結・社内承認が必要です。切り替え条件を派遣元と事前に確認しましょう。
Q2. 3年ルール超過直前に契約解除は可能?
A. 契約満了6カ月前に代替手配や異動計画を立てるのが原則で、直前対応は人手不足を招きます。
Q3. 派遣社員から直接雇用希望が出た場合、断れますか?
A. みなし雇用は派遣先の意思に関わらず発生します。期間管理で超過を回避してください。
Q4. 是正勧告後に改善策未提出だと?
A. 過料命令や企業名公表に移行します。速やかに調査・改善計画の提出を。
Q5. 複数の派遣元を併用した場合でも3年は合算されますか?
A. はい。派遣元が異なっても部署ベースで3年を合算管理する必要があります。
まとめ
本記事では、製造派遣を発注する際に必ず押さえておきたい5つのポイントを解説しました。契約形態の選び方、同一部署3年ルール、みなし雇用の仕組み、違反時のペナルティ、よくある疑問――これらを理解し、正しい運用体制を整えることで、法令違反によるコスト増やトラブルを未然に防げます。
特に3年ルールとみなし雇用は予算計画にも直結する重大リスクですので、配属記録の管理や内部レビューを徹底してください。安心して派遣活用できる組織づくりの一助として本記事をご活用いただければ幸いです。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報