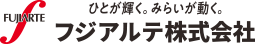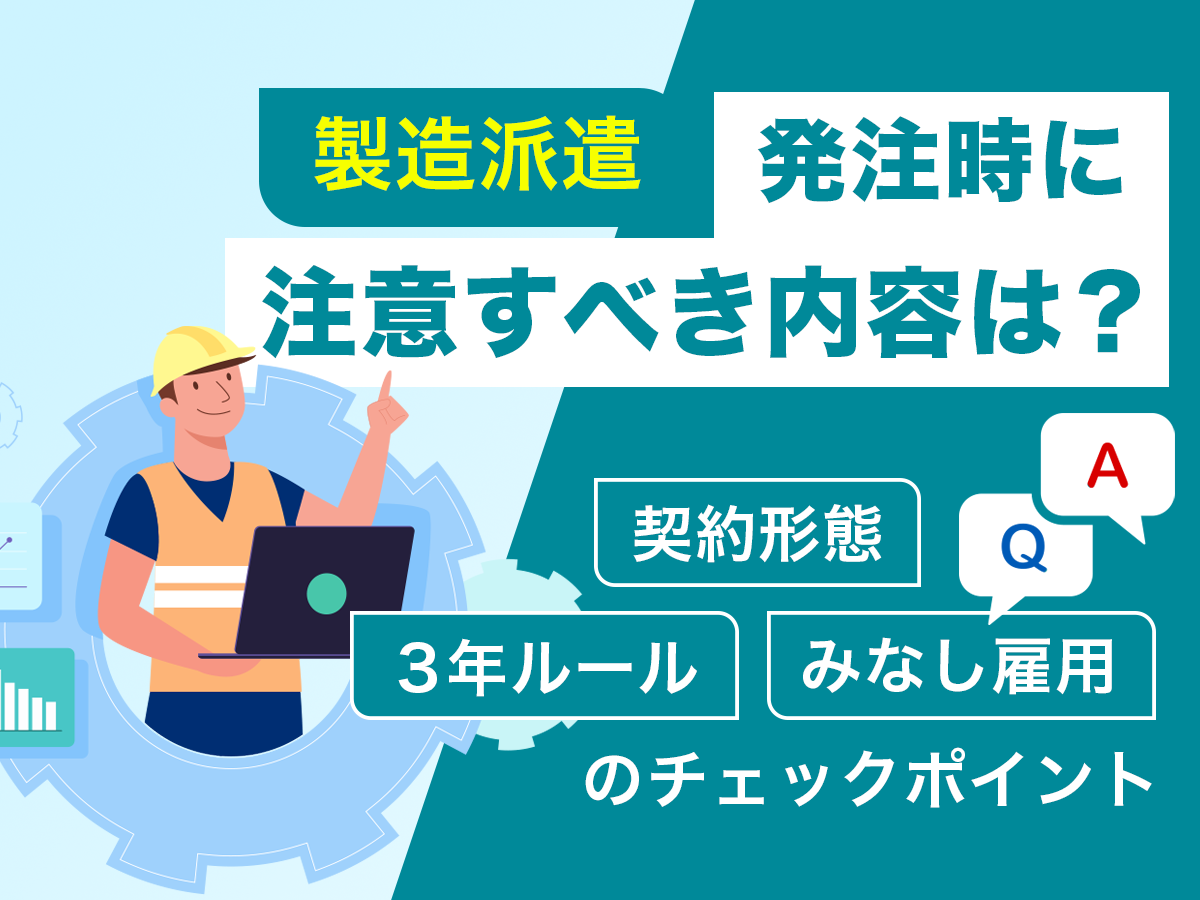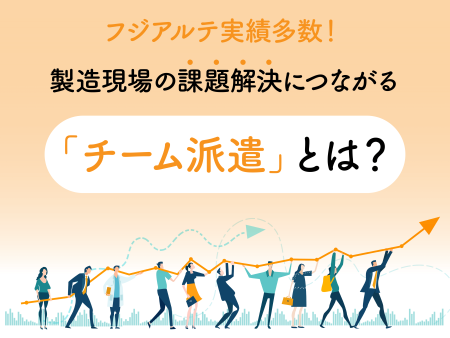派遣コラム
「受入通知書って何のため?」班が違えば“別部署”になる?製造現場で起きがちな派遣法の誤解
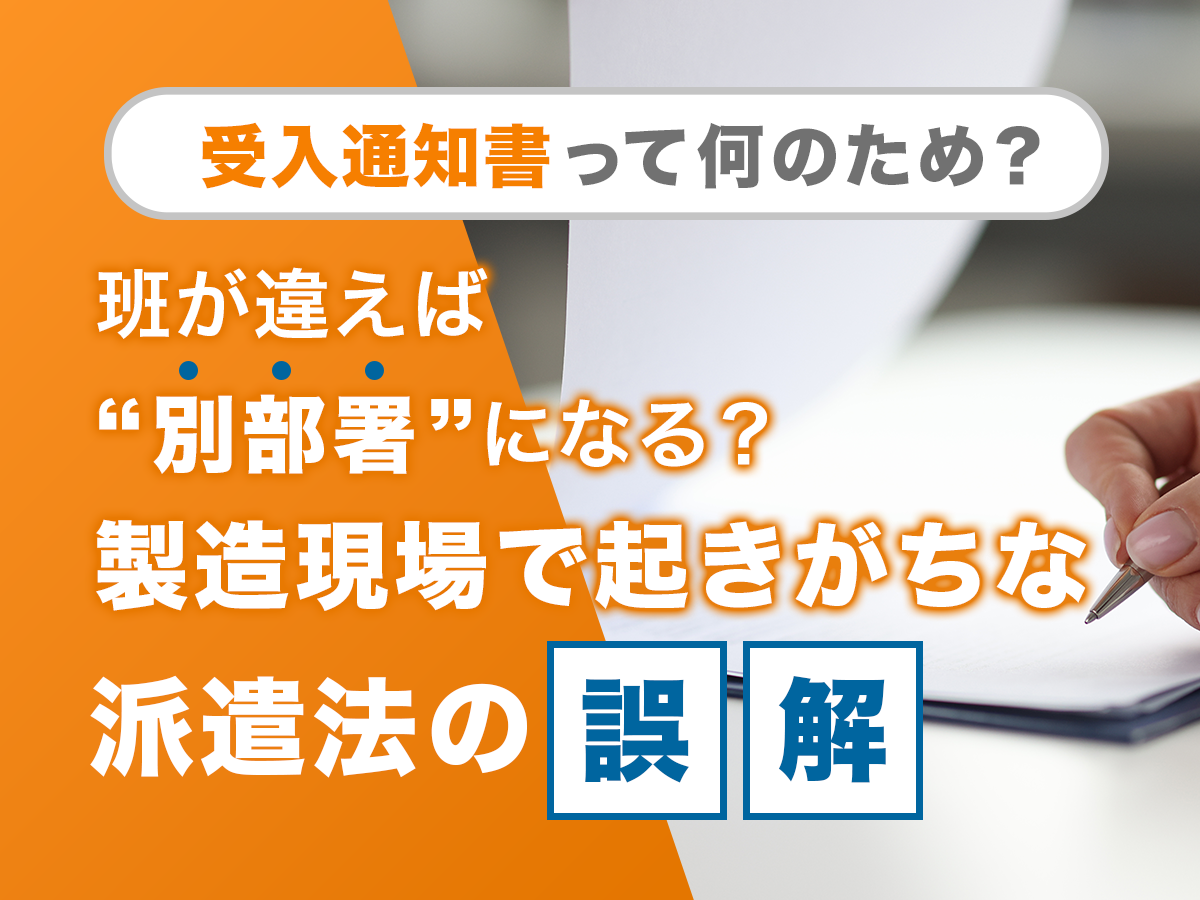
「同じライン内なんだから、新たに通知書なんていらないでしょ?」
派遣の現場では、こんなやり取りが交わされることがあります。
派遣スタッフの受け入れには、法律で「最長3年まで」という期間制限が設けられています。
このルールを適切に運用するためには、派遣先企業が派遣会社に対して「受入通知書」を提出し、受入期間の開始日を明確に伝える必要があります。
しかし、「同じ工場」「同じライン」「似たような業務」など、境界線が曖昧なケースでは、通知書の提出が必要かどうか判断に迷うことも少なくありません。
本記事では、製造業の現場で起こりがちな誤解を事例で紹介しながら、「同一の部署」の考え方と受入通知書の必要性について、わかりやすく解説します。
例|家電メーカーA社
家電メーカーA社では、流れ作業を行っているラインのひとつで製造派遣を利用しています。このラインでは、それぞれ別の工程ごとに1〜4までの班に分かれており、各班で業務内容や作業工程が異なり、指揮命令者もそれぞれの班で異なっていました。
このうち、第1班にはすでに派遣スタッフが就業中です。ある日、第2班では「自分の班で急に欠員が出そうだ」という報告があり、そこでも派遣を利用することになり、派遣会社に追加で1名の派遣を依頼しました。
すると派遣会社の営業担当者から、こう言われます。
「受入通知書が必要となりますので、いただけますでしょうか?」
班長は、「通知書なら最初にお願いしたときに出したし、同じラインだから要らないでしょう?こっちも急いでいるので、余計な手続きは省きたいのですが……」と返答しました。
実はここに、派遣法上の重要なポイントが隠れています。
Table of Contents
そもそも「受入通知書」とは?誰がいつ、何のために出す書類?
派遣先企業は製造派遣を受け入れるにあたり、同一の業務について最長でも3年を超えて受け入れることはできません。この期間は、派遣スタッフがその業務に従事できる期間ではなく、文字通り、派遣先企業が派遣スタッフを受け入れることができる期間となります。
ですから、ある業務について派遣スタッフを追加したり、あるいは派遣スタッフを交代したとしても、受け入れできる期限に影響はありません(派遣スタッフが変わっても、派遣会社が変わっても、受け入れ期間が伸びることはありません)。
このように、受け入れ期限がいつになるかは、派遣先企業の事情によって決まるため、派遣会社や派遣スタッフは派遣先企業に教えてもらわないと、それがいつなのかがわかりません。
そこで、知らないままうっかりと受け入れ期間を超えて派遣(就業)してしまうことのないように、派遣法では、派遣先企業は派遣会社に対して、受け入れ期限の翌日――つまり、派遣受け入れができなくなる最初の日を、書面、ファックス、電子メールのいずれかの方法で、あらかじめ契約前に通知しなければならないと定めています。
この書面を、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日(省略して「抵触日」)を通知する文書ということで、「受入通知書」と呼びます。受入通知書の提出は、派遣先企業の義務ですので、必ず派遣会社への提出が必要です。
「同一の部署」ってどう判断する?班・係・課の分け方がカギに
「同じラインだから同じ業務でしょ?」という感覚は、製造現場ではよくあります。
ですが、派遣法のルールでは、“同じ業務”かどうかの判断は、感覚ではなく組織構造や業務内容に基づいて厳密に決められています。
派遣法の指針では、「同一の業務」の定義として次の2つが示されています。
①「派遣契約を更新して、引き続き同じ業務に従事している場合は、同一の業務と見なす」
→これはいわば“人が変わらなければ同じ仕事”という分かりやすい基準です。
②「派遣先企業の“組織の最小単位”において行われる業務は、同一の業務と見なす」
→こちらが重要なポイントで、“部署や班が同じかどうか”が判断材料になるという意味です。
この②の「組織の最小単位」とは何かというと、法律上は次のように定義されています。
「業務の指示を行う権限を持つ者と、その指示のもとで働く者のまとまりで、最も小さな単位」
つまり、日々の業務で直接指示を出す人(例:班長や係長)と、その指揮を受ける作業者がひとまとまりになっている単位のことを指します。 多くの工場では「班」「係」「グループ」などがこれに該当します。なお、部署名が何であるかは本質ではなく、実態で判断されます。
次の3つの要素がすべて異なる場合は、別の部署=別の業務と見なされる可能性が高くなります:
- 業務の内容が異なる
- 組織の区分(物理的・図上の配置)が異なる
- 指揮命令者が異なる
今回のA社のケースでは、各班で作業内容・場所・指揮者が明確に分かれているため、「第1班」と「第2班」はそれぞれ別の部署、つまり別の“受け入れ枠”として扱われます。
したがって、第2班で新たに派遣スタッフを受け入れる場合には、新たな「受入通知書」の提出が必要となるのです。
名称より中身が大事!部署が違って見えても“同一”とされるケース
先ほど述べたように、「最小の単位」は実態に即して判断されます。そのため、部署名が異なっていても、実際の業務内容や指揮命令系統が同じであれば、「同一の部署」とみなされるケースもあり得ます。
たとえば、いくつかの班に分かれてはいるものの、各班の業務内容がまったく同じで、指揮命令者も1人がすべての班を兼任している場合、これらの班は「ひとまとまり」として同一の部署と判断される可能性が高くなります。
部署をまたいでも「抵触日」は共有される?知らずに違反の恐れも
今回のケースでは、派遣会社の営業担当者が「受入通知書が必要になります」と述べており、第2班は第1班とは別の部署として手続きされているようです。
このように、業務内容や指揮命令系統が明確に分かれ、かつそれぞれに対して個別に受入通知書が提出されていれば、受入枠も別扱いとなり、抵触日も独立してカウントされます。つまり、第2班に第1班の抵触日が適用されることはありません。
しかし、実務の現場では以下のような運用ミスが起きることがあります。
- 最初に提出した受入通知書の範囲があいまいだった
- 派遣契約書の業務欄が「ライン全体」とされていた
- 第2班の新規受入時に通知書を再提出していなかった
このような場合、制度上は「ライン全体で1つの業務枠」とみなされ、第2班の派遣が“第1班の継続”と解釈される可能性があります。結果として、既に第1班でカウントが始まっていた受入期間が適用され、第2班にも第1班の抵触日がそのまま引き継がれるリスクが生じます。
この状態で「第2班はまだ3年経っていない」と誤認し、派遣を継続すると、抵触日を超えての受入れとなり、重大な法令違反に発展する可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、部署ごとに業務内容や組織構造の違いを明確にし、個別に受入通知書を提出する必要があるかどうかを、派遣会社と事前に十分にすり合わせておくことが不可欠です。
現場だけで判断せず、必ず派遣会社にご相談を!
「同一の部署かどうか」の判断基準は、派遣の受け入れ期間制限を形だけ逃れようとする“脱法的な行為”を防ぐために「実態で判断する」というルールが設けられています。
その一方で、この“実態主義”が判断を複雑にしているのも事実です。
そのため、現場だけで判断せず、派遣会社の営業担当者に相談し、必要があれば派遣会社の法務担当者など専門部署と連携して確認することが、適切な運用には欠かせません。
まとめ|法令順守と安定稼働の両立のために
製造業の現場では、ラインや工程が複雑に分かれており、「どこまでが同じ部署なのか?」という判断に迷う場面が多くあります。
しかし、派遣スタッフの受け入れに関わるルールは、法令で明確に定められており、たとえ小さな判断ミスでも重大な違反につながりかねません。
今回ご紹介した「受入通知書」や「同一の部署」の考え方は、派遣契約を適正に結び、現場を安定稼働させるうえで非常に重要な基礎知識です。
フジアルテでは、現場の実情に応じた制度運用をサポートするため、事前のヒアリングや法的観点からのアドバイスを丁寧に行っております。
「自社の判断が正しいか不安」「通知書をどう出せばよいか分からない」といった場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事の執筆者
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報