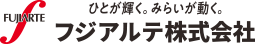労務管理Q&A
地方労働行政運営方針が発表されました。 製造業に影響があると思われる指導方針はあるのでしょうか。
ご質問内容
地方労働行政運営方針が発表されました。
製造業に影響があると思われる指導方針はあるのでしょうか。
専門家からの回答
地方労働行政運営方針は、厚生労働大臣から都道府県労働局長あてに、都道府県労働局がその年度に取り組むべき行政課題について通達したものです。
運営方針では、労働基準監督署や需給調整事業課などが、何に力を入れて調査をするのか、どんな指導をする予定かなどが明らかにされています。
冒頭は「中小企業の賃上げ」「非正規の待遇改善」
昨年度の最低賃金の改定により、最低賃金の全国加重平均が1,055円となりました。
令和6年11月22日の閣議決定「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」をうけて、最低賃金の全国加重平均1,500円を2020年代のうちに達成することを目指す旨の記載があります。
昨年度の行政運営方針では2030年代に実現を目指している旨の記載でしたから、前倒しの表明となり、予想より短期間に人件費の高騰が見こまれます。
賃上げと併せて「非正規労働者の待遇改善」「同一労働同一賃金」についても、労働基準監督署が臨検時に把握した内容を、都道府県労働局雇用環境・均等部(均等室)および職業安定局需給調整事業課(室)と情報共有するほか、基本給・賞与について正社員との待遇差がある理由の説明が不十分な企業に対し、点検要請を集中的に実施する予定です。
したがって、各社では、正社員と短時間・有期雇用労働者とで、給与・賞与だけではなく様々な手当や制度に相違がある場合、その相違の理由を合理的に説明できるかどうかが問われます。
なお、有期雇用労働者の無期転換制度にいては引き続き促進姿勢であり、「無期転換ポータルサイト」においてワンストップで情報を提供し、労働者からの問合せにも応じるなど、転換の権利を知らない労働者への周知啓発に力を入れています。
昨年、改正労働基準法施行規則が施行され、無期転換権が生ずる労働者を対象として労働条件通知書に「無期転換の申込み機会」「無期転換後の労働条件」について明示することが義務になりました。
4~5月は、若手の労働基準監督官による「総合労働条件調査」のシーズンです。労働条件通知書の記載事項はしっかり点検される傾向にありますので、今一度、明示事項は法令が求める内容かどうかをご確認下さい。
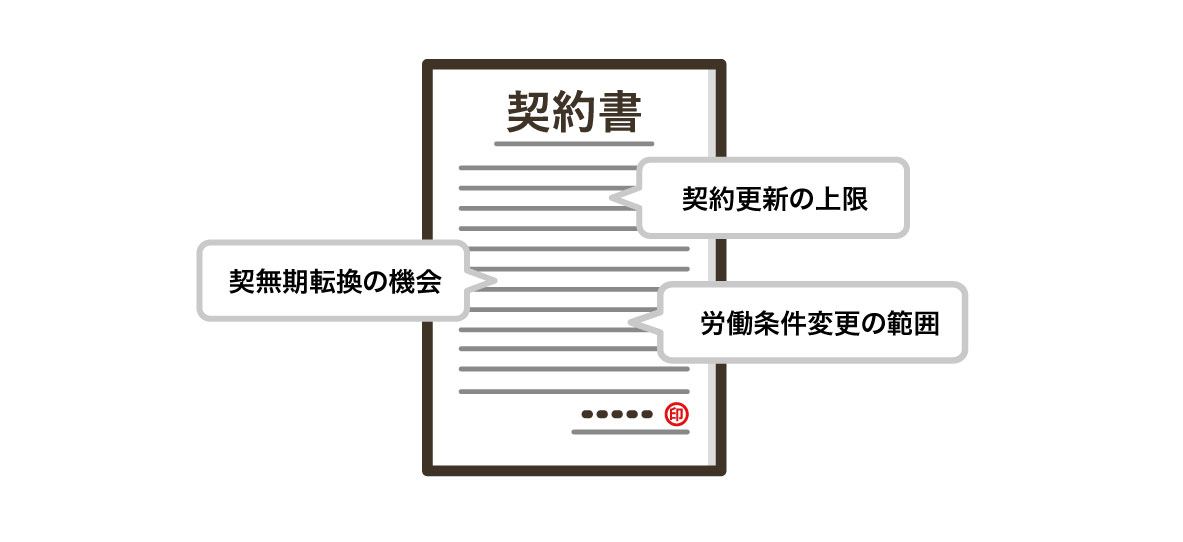
人手不足で加熱する悪質な人材仲介会社への規制
人手不足から転職市場が加熱しており、高額な紹介手数料の請求や、求人を取り下げたいのに解約できないなどのトラブルが増加しています。
このような状況を受けて、昨年の職業安定法および関連法令の改正によって、求人事業主と求職者との労働契約成立をあっせんする有料職業紹介事業者および転職情報等を広告やインターネットサイトに掲示する募集情報等提供事業者(情報提供のみであっせんはしない)に対し、いわゆる「お祝い金」など求職者への金銭の提供が禁止されました。
「お祝い金」を目当てに短期間に転職を繰り返す求職者を封じ、またそのような行為を助長する人材仲介会社等への規制が強化されています。
また、手数料や違約金および解約の方法などの情報開示が義務化されました。
求人される会社は、運営主体が不透明なサイトなどを安易に利用せず、平素からつきあいのある派遣会社や職業紹介事業者にまず相談して市場動向や相場に関する情報を得るなど、充分注意してください。
なお、今年度の方針で、はじめてアプリを経由した「スキマバイト」「スポットワーク」について言及し、アプリを運営する事業者に法令違反がある場合は指導を徹底する方針が示されています。
ジョブ型人事の導入促進
令和6年8月28日に「ジョブ型人事指針」(内閣官房、経済産業省、厚生労働省)が発表されました。
これまでわが国で主に採用されてきた勤続に対する給与を見直し、従事する業務の内容の難易度や責任の程度に応じた「職務給」制度の整備をすすめる方針が示されています。
このようなジョブ(職務)と賃金がリンクすることで公正な処遇をすすめ、ひろく「非正規労働者の処遇の改善」も含めた「同一労働同一賃金」の推進がはかられそうです。
なお、「配偶者手当」は、社会保険制度とあいまって主に女性の就労を抑制しているとの指摘があり、見直しが推奨されています。
多様な人材の活躍
〇高年齢者
全労働者に占める60歳以上の労働者の割合は18.7%(令和5年)ですが、休業4日以上の死傷者に占める割合は29.3%と、高年齢者の業務災害が増加しています。
高年齢労働者の労働災害防止対策等を支援するための補助金(エイジフレンドリー補助金)は令和7年度に拡充の予定ですから、設備メンテナンスの際にスロープの設置や工程の機械化等、補助金を活用した物理的な環境整備も考えてはどうでしょうか。
〇仕事と育児との両立
産後パパ育休制度によって、短期間ではあるものの男性の育児休業取得率が飛躍的に伸びています。
改正育児・介護休業法は4月と10月に段階的に施行されますので、就業規則等の整備についてご確認下さい。
令和7年度値地方労働行政運営方針についてご質問がある場合は、営業担当にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者

- 北桜労働法務事務所 特定社会労務士
- 株式会社北桜戦略人財研究所代表取締役社長
- 株式会社北洋銀行 社外取締役監査等委員
- プロフィール
-
平成6年4月、旧労働省入省。鹿児島労働局、本省、北海道労働局にて需給調整指導官等を歴任。
平成20年3月に厚生労働省を辞職、札幌に北桜労働法務事務所を開設。
行政経験を活かし、人材ビジネス分野を中心に労務全般に強い社会保険労務士としてコンサルティングを行っている。
公式HP
製造業の人事・労務の最新情報をメルマガで
いち早くお届けします!
- 人材派遣の業界ニュース、関連法案の見解
- 労働問題のお悩みに専門家が詳しく回答
- コンプライアンス・セミナーの開催情報