製造派遣・製造請負で
経営課題を解決
「品質を維持し、ムダな費用をかけずに納期を遵守。かつ安全に。」を意識し課題解決に貢献します。


製造に特化した人材派遣や人材紹介、紹介予定派遣などの人材サービスをニーズに合わせてお選びいただけます。
さまざまな条件にも柔軟な対応が可能となり、チーム派遣の形式での導入ではコミュニケーションや業務管理も管理者にお任せいただけます。
“製造領域に付随した業務”に強いエンジニアが常駐してビジネスをサポートします。
適正配置と丁寧なフォロー体制による高い定着率を実現します。製造現場の活性化に貢献します。
提案力とものづくりの実績を活かし、QCDS活動を行いながら生産性向上を実現します。
半導体事業・モビリティ(自動車)事業
教育訓練施設や独自のプログラムにより、育成後に企業様へ弊社社員を円滑に配属します。

| 業界・業種 | 金属等の容器メーカー |
|---|---|
| 部門・職種 | 金属製品製造 |
| 従業員数 | 1,000名以上 |
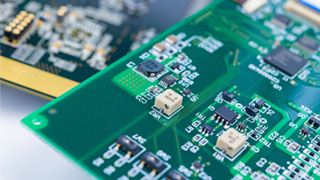
| 業界・業種 | 電子部品 |
|---|---|
| 部門・職種 | 電子部品製造 |
| 従業員数 | 300名以上 |

| 業界・業種 | 金属製品 |
|---|---|
| 部門・職種 | プラスチックフィルム製造 |
| 従業員数 | 1,000名以上 |
お客様のニーズへの対応はもちろん、製造現場の課題を解決し、生産性を向上させ、
明日の社会をより豊かにしていくための人材サービス会社です。




総合人材サービス業界のパイオニアとして創業以来培ってきた独自のノウハウから、厳選した事例や人材活用のポイントをご紹介します。
製造業に特化したホワイトペーパーをぜひご活用ください。

製造派遣や製造請負を通じて、自動車、電子機器、半導体など、ものづくりの現場を支えてきた、創業より60年以上の歴史を持つ総合人材サービス会社です。
「一人ひとりの社員の成長がお客様への価値あるサービスの提供につながる」という信念のもと充実した教育・研修制度の提供を通じて、積極的に支援します。